最近、「自分で考えて、決めて、行動する」という、ともすれば当たり前のことを改めて考えている。(“考えることを考える”って、ちょっと変だけど)
忙しい日々の中では、体が覚えた「いつものやり方」に流されてしまいがち。だけど、ときどき立ち止まって「これは本当に自分の頭で考えた結果だろうか?」って考える必要があるよな、と。そんなひとときの時間をつくることが、次の一手、次の一歩をより良くしてくれるはず。
このときの「考える」は、誰かに言われてから動くこと、つまりお題を与えられて考え始めるのではなく、自分なりの理想像――「こうありたい」「こうなると良い」を描き、目の前の現状を観察して、その理想とのギャップを見つけることにある。ギャップが見えれば、埋めるための仮説も立てやすいから。
もうひとつの「決める」は、選び取る力だと思う。
人に相談する。過去の事例をあたる。別の視点から考えアイデアを出す。——そうして複数のルートを並べ、最後は自分の責任で「これでいく」と腹を決める。だからこそ、どんな結果でも納得できるし、そこから得たものは学びとなり次につながる。
長く同じような仕事、同じようなことを続けていると、深く考えずに前例や慣習に流されがち。それはとても便利(というかラク)だけど、「本当に最善か?」「他に良い方法は?」と疑ってみる。誰かを否定するための“疑い”ではなく、より良くするための視点をもつ。そうしてフラットに見直したうえで、「これが良い」と決めたら、自分の選択を信じて踏み出す。
ちなみに、「自分で考える」については、上司部下の関係においては「目標と権限設定の曖昧さ」と「上司の口出しすぎ」もあると思うので要注意。部下がちゃんと考えてくれない、ってグチはたいてい自分に責任があると疑わないと。他責もラクなしぐさだよね。
自戒しつつ、自分も周りも、考える力と選び取る力を養っていけるよう、これからも丁寧に向き合っていきたい。

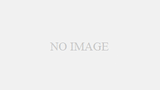
コメント