自分の本棚や読書履歴を開陳するのはけっこう恥ずかしい…ことだと想うけど、立て続けに他の方がnoteに投稿していた読書メモを見ていてちょっと書いてみたくなったのでメモ。
小説…と言えるような本を最初に読んだのは何だったろう?
小学校の高学年くらいで、ドラゴンクエストのノベライズを読んだ記憶がある。町内にあった、文具店を兼ねる小さな書店に取り置きしてもらい、自転車を立ちこぎしながら取りに行った記憶。
その後は、いわゆるファンタジー小説。ロードス島戦記にハマり、クエスト系の色んなライトノベルを手当たり次第に読んでいた。マンガを読むよりもこういった冒険物語を読むことが好きだったかも。これは、小学校時代の探検遊び(造成中の工事現場や林のなか、知らない場所を、おやつや飲み物を持参して探検して回る遊び)がもっと壮大なスケールになっていたのが楽しかった。
毛色が変わったのが大学生になってから。学校や一人暮らしのアパートのそばの本屋でやすい文庫を見繕って読むことが増えた。今振り返ってみれば、とうじそばにいた先輩や同級生がそうやって本を読んでいたのに感化されていたのだと想う。勝手に一目置いていた一浪の同級生がすごいという辻仁成の小説を片っ端から読んでみたり、お酒に溺れるように中島らもの小説を読みふけったり。一方で、ブックオフ等で見かけた梶井基次郎や太宰治、三島由紀夫も読み漁ってたな。辻仁成から恋愛小説?というジャンルを知って、石田衣良とか桜井亜美とか。ちょっと好きだった子に紹介された山田詠美とか、江國香織とか、村上春樹とか。
大学の3-4年生のころは、宮台真司の話に「そんなことになってるの?」と驚き、辺見庸の「もの食う人々」に衝撃を受け、中谷彰宏のレストラン王たちの話にフードサービスへの想いをつのらせていた。多分、このころは自分の性向をなんとなく理解し、「食」というものへの興味関心を深めつつ、人間の「欲」や人間関係、「生きていくことのままならなさ」をどうつかみ取り組むか?ということをずっと悩んでいたような気がする。
大学4年間は、時間とお金があれば国内を旅していた。その時も、普段の通学やバイトへ向かう時も、チノパンのポケットには文庫か何かがあり、カバンを持っていればポケットサイズの国語辞典も持ち歩いていた。
読書が自分の考えを形づくってくれた、という側面は大いにあったと思う。同時に、自分が興味を持てる分野や感覚のあう作家を選んできたからこそ、自分の考えや価値観がより具体化していったということもあると思う。
社会人になった今は、ビジネス書や職種ならではの本も読むし、小説も、雑誌類も、哲学の本も読む。AIと壁打ちしながら理解を深めることもあるし、実際の仕事で活用してみることも多い。自宅の本棚は食に関する物語や資料集であふれていて、それ専門のブックカフェが出来そうなくらい。
こうやって振り返ってみると面白いですね。
単純にファンタジー系ラノベが好きだった、ではなく、本に出会う前の自分の好奇心や冒険心がベースにあったことに気づくことになろうとは。
人生80年、100年。
まだまだ知らない本との出会いを楽しみにしたいと思います。

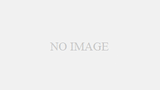
コメント